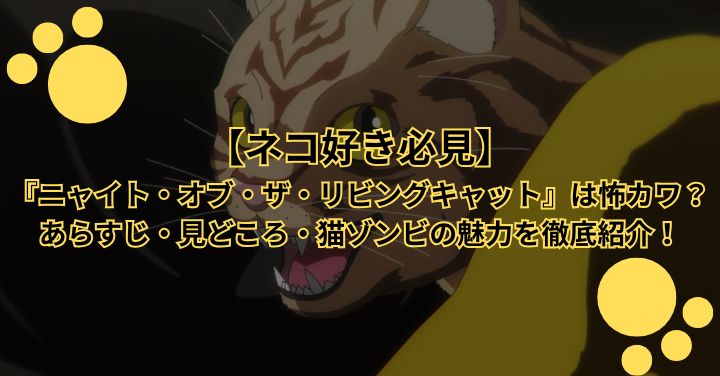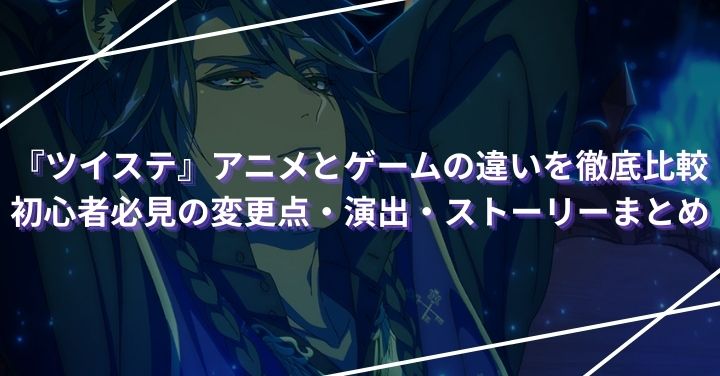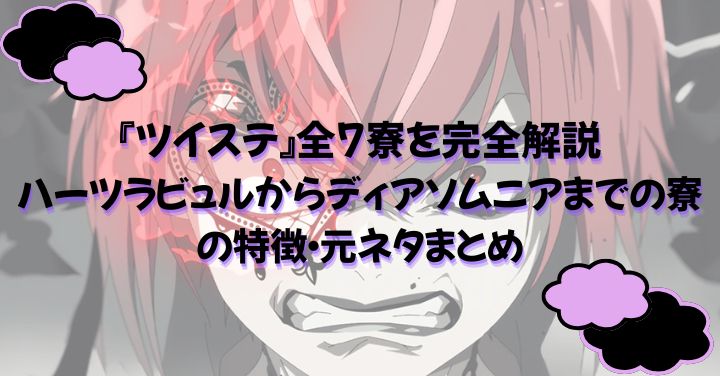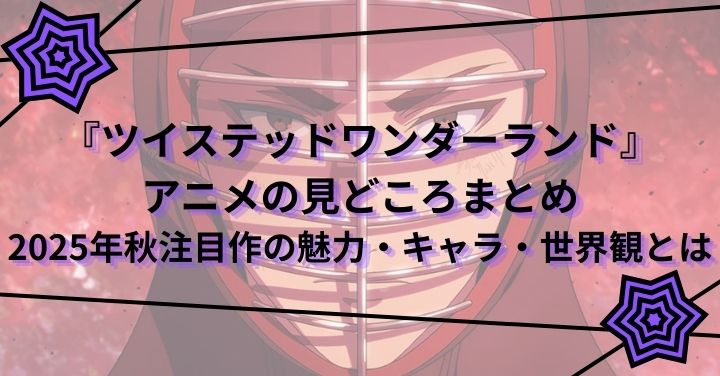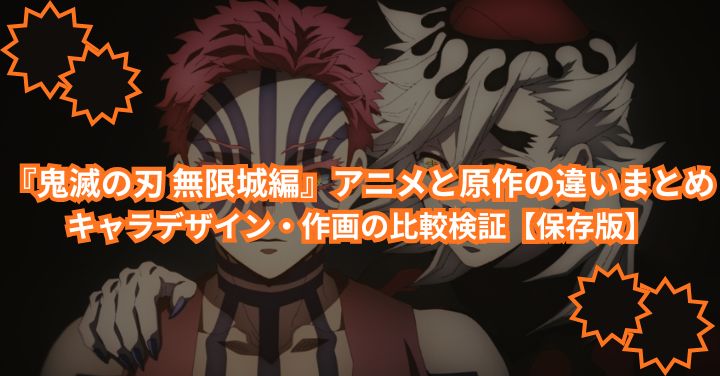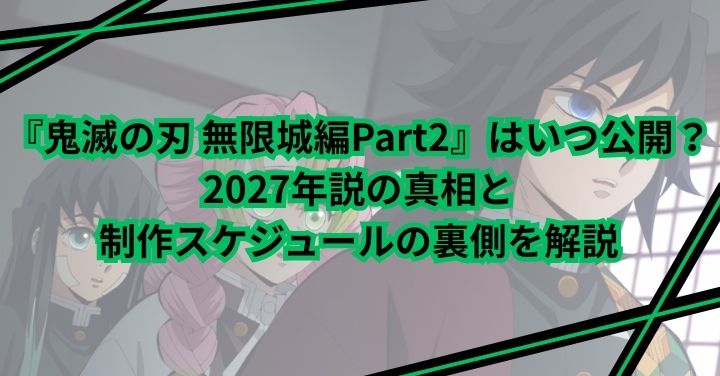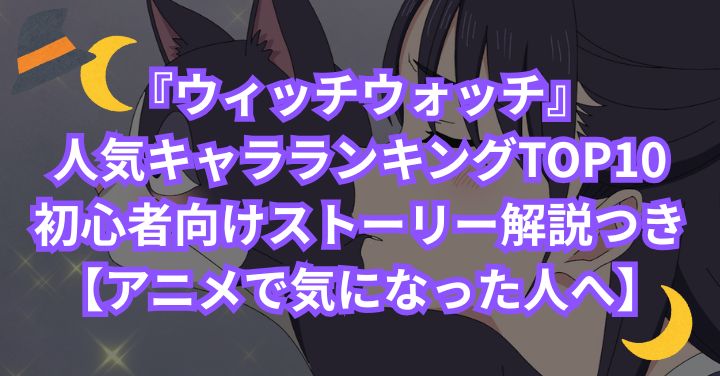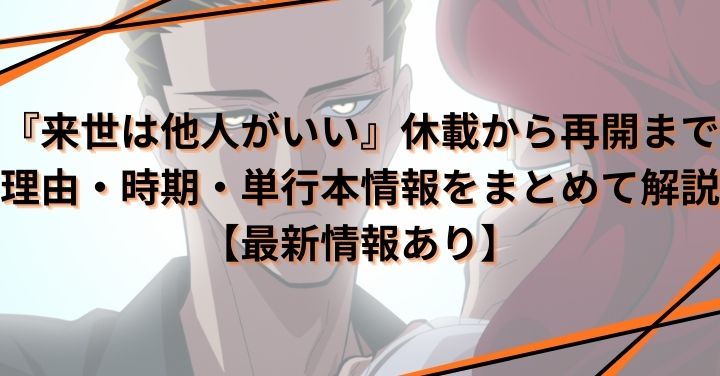『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、“猫ゾンビ”という異色の設定で話題を集める、今もっとも注目すべきホラーコメディ漫画です。
この記事では、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のあらすじや見どころを通して、その“怖カワ”な世界の魅力を徹底的に紹介します。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』が注目されている理由は、単なるホラーやギャグではなく、「猫の可愛さ」と「人類の恐怖」を同時に描くという唯一無二の構成にあります。
可愛い猫にスリスリされると“感染”して猫化してしまうという発想が斬新で、読者は恐怖よりも先に“愛おしさ”を感じてしまうのです。
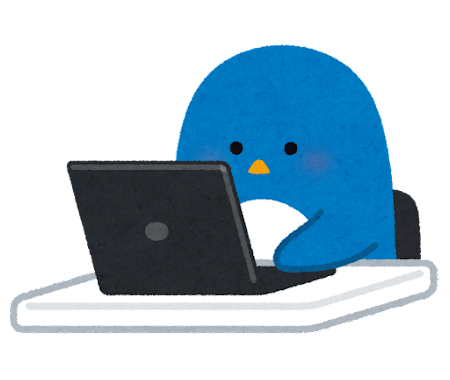 リサーペン
リサーペンそのギャップが、他のホラー作品にはない強烈な印象を残しています。
たとえば、あらすじでは世界が“猫化ウイルス”により崩壊し、人類が猫に変えられていく様子が描かれます。
主人公たちはこの“癒しの終末”を生き抜くために奔走しますが、次々と現れる猫ゾンビの愛らしさに抗えず、読者もまた不思議な感情に包まれます。
見どころとしては、ホラー特有の緊迫感と、猫の柔らかい仕草や表情が織りなす“癒しの破壊力”。
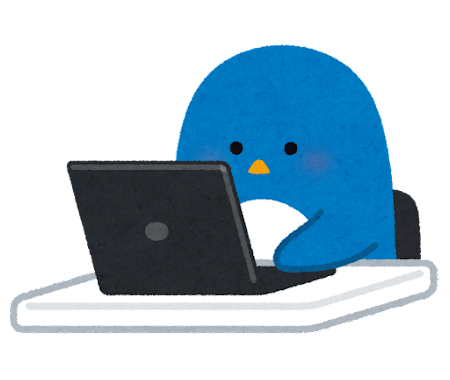
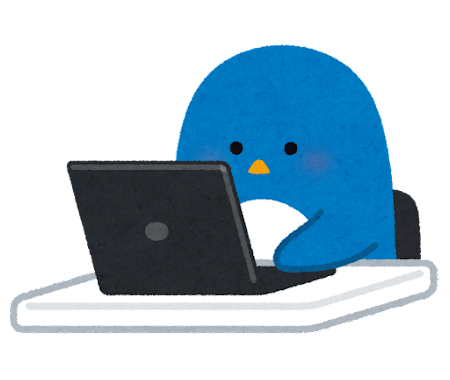
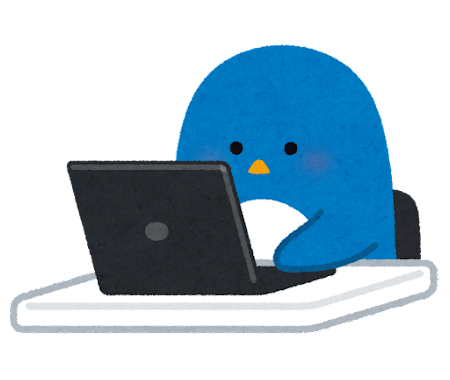
恐怖と癒しが同時に訪れる、その瞬間こそが『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の真髄です。
つまり、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、“怖い”だけでも“可愛い”だけでもない、新感覚のエンタメ体験を届けてくれる作品です。
あらすじを追うほどに深まる物語の魅力、そして思わず笑ってしまう数々の見どころを知れば、あなたもきっとこの“猫ゾンビワールド”の虜になるはずです。
\ニャイト・オブ・ザ・リビングキャットを観るなら無料で観れるABEMAがオススメ/
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』とは?あらすじ&基本情報まとめ


「猫が世界を滅ぼす?」
そんな一文に心をくすぐられる方は多いのではないでしょうか。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、かわいすぎる猫たちが人類を“猫化”させていくという、奇想天外な設定で話題を呼んでいる作品です。
この章では、原作の基本情報から物語の舞台設定、そして「人類が猫になる」という衝撃のあらすじまでを徹底解説します。
猫好きもホラー好きも、まずはこの異色の世界観を一緒に覗いてみましょう。
原作はどんな作品?作者・掲載誌・ジャンル紹介
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、人間が「猫に触れると猫化してしまう」という前代未聞のパンデミックを描いたホラーコメディ漫画です。
原作はホビー系漫画誌「月間コミックガーデン」で2020年から連載スタート。
| 原作 | ホークマン |
| 作画 | メカルーツ |
タイトルからもわかる通り、名作ホラー映画『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』のパロディを思わせる作品名ですが、内容はただのゾンビパロディではありません。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の「ゾンビ」にあたる存在は、人類を襲う“猫”。
しかもその猫たちは可愛く、もふもふで、愛らしい仕草を見せながらも、人間社会を滅ぼしていく。



怖いのに癒される。



ホラーなのに幸福感がある。
このような声も上がるほど他にない魅力を放っています。
ジャンルとしては、以下の要素が組み込まれている。
- ホラー
- コメディ
- パニックサバイバル
- 癒し
読む人によって「可愛い」「怖い」「シュール」と感じ方が大きく変わる点が特徴です。
特に猫好きの読者からは以下のようなコメントも寄せられ、SNSでも話題を集めています。
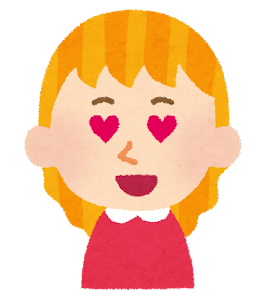
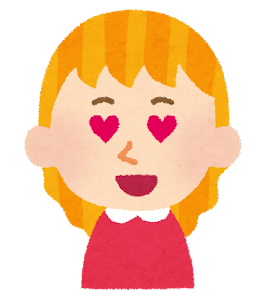
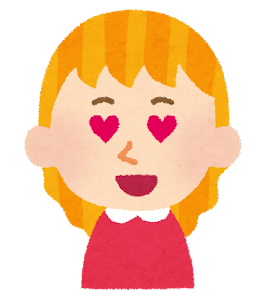
こんな終末なら悪くない!
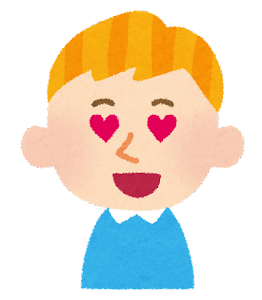
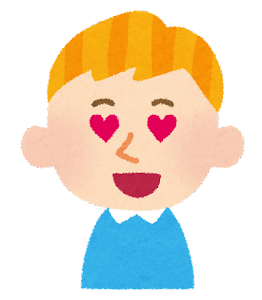
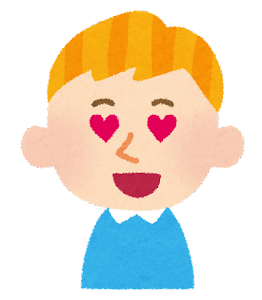
全人類が猫になる世界、むしろ平和では?
また、作画を担当するメカルーツ氏は、緻密な猫の描写力とデフォルメのバランス感覚に優れた絵師として知られ、毛並みや仕草の一つひとつまで“本物の猫愛”が伝わる筆致が人気の理由です。
可愛いのに恐ろしい、癒しと終末が共存する世界を、ここまでリアルかつポップに描ける作家は他にいないでしょう。


猫好きもゾンビ好きも楽しめる!独特の世界観とは
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の最大の特徴は「感染源が猫」という点。
この世界では、人間が猫に触れられた瞬間に“キャット化”し、記憶や言葉、人間としての意識をすべて失い、ただの猫になってしまいます。
ゾンビのように人間を襲うわけではなく、可愛すぎるアプローチで人類を滅ぼすのです。
・すり寄ってくる
・撫でてほしそうに見上げてくる
通常のゾンビ作品では、「噛まれる」「傷を負う」などの恐怖を伴う感染ですが、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』では「愛らしさ」「癒し」が感染経路。
つまり“猫のかわいさ”という抗えない魅力が、人類最大の脅威になるのです。
人間たちは感染を避けるため、マスクや防護服を身につけ、街中の猫を避けながら生活を続けています。
しかし、道の角を曲がればそこに“ごろにゃん”と座る猫、廃墟の中で小さく「にゃー」と鳴く声……その一瞬の油断で、人間はまたひとり猫へと姿を変えてしまいます。
この「可愛い=恐怖」という構図は、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』ならではのブラックユーモア。
ゾンビの代わりに“猫”を置き換えることで、従来のホラーとは真逆の感情を呼び起こします。
読者は「逃げなきゃ」と思いながらも、「でも触りたい」「モフりたい」というジレンマに襲われるのです。



また、作品全体のトーンは単なるギャグではなく、社会風刺的な一面も。
人類が「かわいさ」や「癒し」を求めすぎて滅びる。
このような皮肉めいたメッセージが隠れており、読み進めるほどにその深みが見えてきます。
まるで癒し依存社会への風刺のようでもあり、SNS時代の「猫動画文化」へのユーモラスなオマージュとも言えるでしょう。


人類が「猫化」していく!?衝撃の設定を解説
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の簡単なあらすじをご紹介。
物語の舞台は、突如として世界中に“キャット感染”が広がった近未来。
原因不明のウイルスによって、人々は次々と猫へと変わっていきます。
感染のきっかけはただひとつ、猫に触れること。
毛一本、肉球のタッチ一つでもアウト。
人類は“もふもふ”の誘惑に逆らいながら、生存をかけた逃避行を続けることになります。
主人公は、猫カフェ勤務のクナギ。
記憶の大半を失っているものの、なぜか猫に関する知識だけは鮮明に覚えている。
驚異的な身体能力を持ち、猫すらも翻弄する俊敏な動きで仲間を救ったり、危機を切り抜けたりすることが多い。


接触感染により広がるウイルスの脅威に猫を愛でることもできずに逃げ惑うばかり。
その道中では、次々と可愛いのに恐ろしいキャットたちが登場します。
- 廃ビルを占拠する「野良猫の群れ」
- 猫タワーのような高層建築に棲みついた猫たち
- 元人間だったことを思わせる、妙に人懐っこい猫
どのエピソードも一見“癒し系”に見えて、次の瞬間には“ホラー”に転じるギャップが絶妙です。
やがて物語が進むにつれ、読者は気づきます。
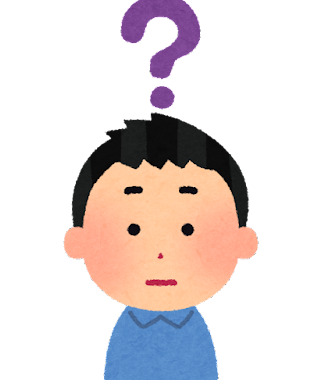
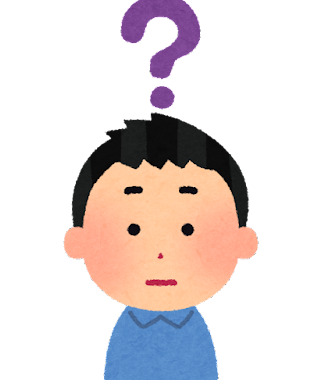
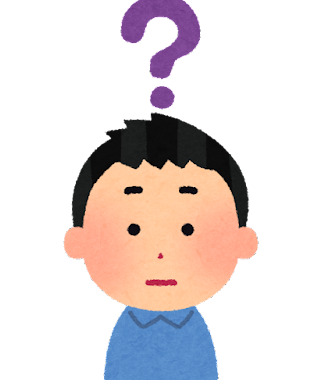
この世界では、猫化した人々が単なる「動物」ではない?
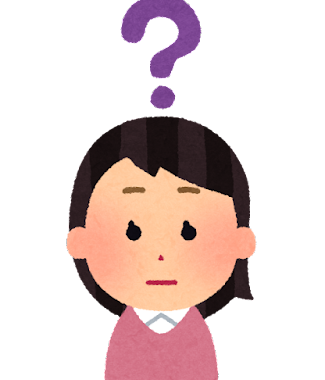
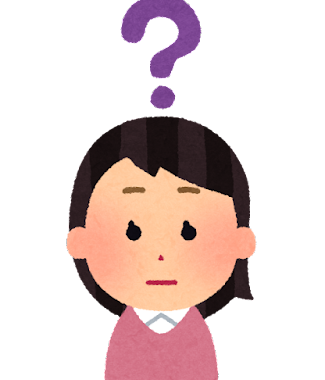
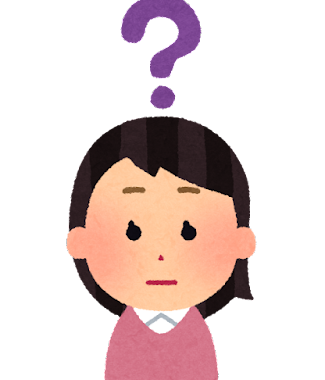
人間だった頃の記憶や感情をわずかに残しているのでは?
クナギが出会う一匹の猫が、かつての友人だったかもしれない。
そんな切なさが、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』全体に不思議な余韻を与えています。
一方で、クナギ自身も猫への愛情を抑えきれず、たびたび“モフりたい衝動”に駆られるシーンも描かれます。
その描写はどこかコミカルでありながら「好き」という気持ちが破滅を呼ぶという逆説的テーマを浮き彫りにしており、ホラーとしても非常に完成度が高いです。
また、作中の演出面でも細やかな工夫が凝らされています。
- 廃墟に差し込む光の中で毛並みがふわりと揺れる描写
- 足音の代わりに“カリカリ”と音を立てて歩く猫の姿
ページをめくるたびに静寂と緊張が同居する独特の空気が漂います。
まさに「サイレントホラー×癒し系日常漫画」という、新ジャンルの開拓者といっても過言ではありません。


『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、猫好きもゾンビ好きも唸らせる新感覚ホラーです。
- “猫に触れたら終わり”というシンプルながら秀逸な設定
- 愛らしいのに恐ろしいキャラクター
- 社会風刺を感じさせる世界観
すべてが高いレベルで融合し、「怖カワイイ」という唯一無二のジャンルを確立しています。
ホラー漫画としての緊張感を保ちつつ、読後感には「モフりたい…」という禁断の余韻を残す。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、猫を愛するすべての人にとって“罪深い快楽”のような作品です。
“怖カワイイ”の正体!作品の見どころと注目キャラ


「かわいいのに、なぜこんなに怖いのか?」
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』を読んだ多くの人が抱く、この不思議な感覚。
そこには、単なるギャップ萌えではなく、“かわいさ”という概念そのものをホラーに転換する独自の発想と構成力があります。
この章では、そんな“怖カワイイ”の正体をひも解くために、作品の見どころと主要キャラクターの魅力、そして作画・演出・セリフの表現技法までを徹底的に掘り下げていきましょう。
猫ゾンビ=「キャット化」の恐怖と愛らしさのギャップ
まず特筆すべきは、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』が描く「恐怖の本質」が従来のホラーとはまったく異なる点です。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』における“感染”とは、痛みや死を伴うものではなく、幸福に包まれながら失われていく恐怖です。
猫たちは決して人間を攻撃しません。
むしろ、人懐っこくすり寄ってきて、ゴロゴロと喉を鳴らし、撫でてほしそうに見上げてくるのです。
その姿があまりにも愛らしいため、人々は自ら猫に触れにいき、結果としてキャット化してしまう。
この“自ら滅びを選ぶ”という構図こそ、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』最大のホラー要素です。
従来のゾンビものが「外的な暴力による破滅」を描いてきたのに対し、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』では、「癒し」や「かわいさ」といったポジティブな感情が破滅の引き金になるという真逆のアプローチを取っています。
この設定が読者に与えるのは、単なる恐怖ではなく“罪悪感を伴う魅力”です。



この猫を撫でたい!でも撫でたら終わり…
この感情の狭間で揺れる緊張感が、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』全体に独特の中毒性を生み出しています。
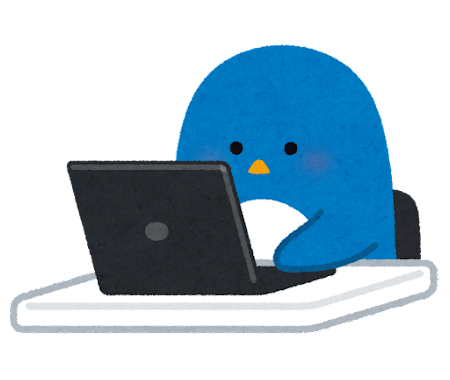
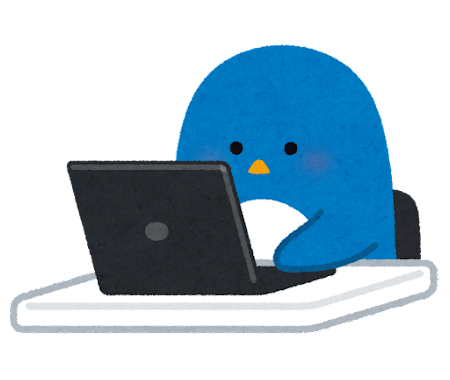
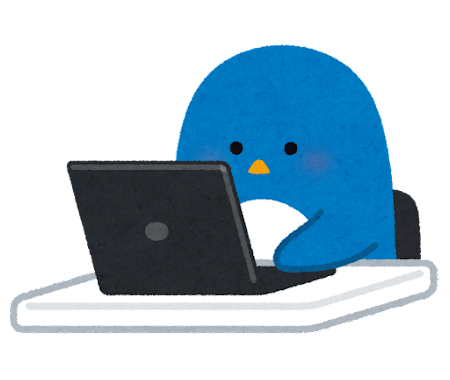
さらに、キャット化した人々も決してグロテスクな存在ではありません。
見た目は普通の猫でありながら、どこか人間だったころの名残を漂わせる。
- 表情
- 仕草
- 居場所の選び方
これらが“かつての記憶”をほのめかすことで、読者は「この猫、もしかして……?」という切ない想像を掻き立てられます。
つまり、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の怖カワイイとは「可愛さが恐怖を上書きする」のではなく、「恐怖の中にこそ可愛さが潜んでいる」という二重構造の心理演出によって成り立っているのです。


主人公クナギと猫たちの関係が描く“癒しと狂気”
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の中心人物であるクナギは、もともと無類の猫好き。
世界が崩壊してもなお、「猫を撫でたい」という衝動を抑えきれない彼は、読者にとっての“感情の代弁者”でもあります。
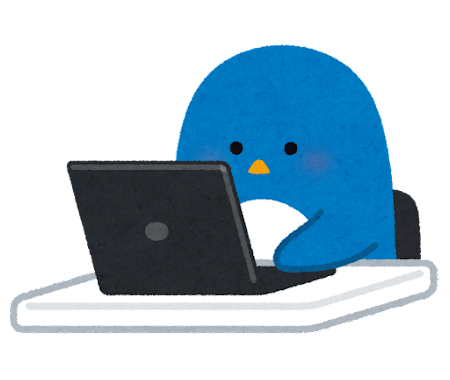
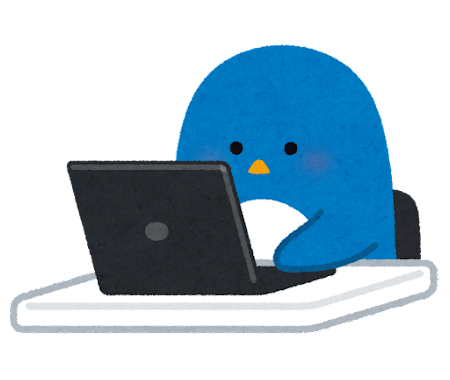
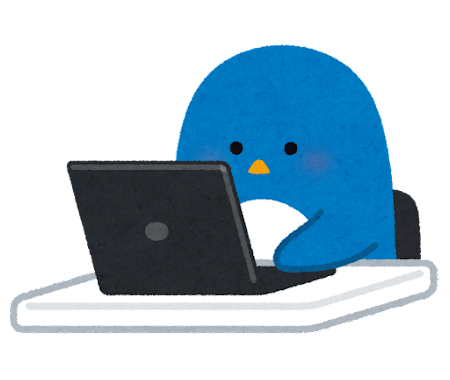
クナギは人間の生存をかけて猫から逃げる立場。



しかし猫を見るたびに心が揺れる…
それは理性と本能、癒しと恐怖のせめぎ合いであり、彼の葛藤そのものが『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のドラマ性を支えています。
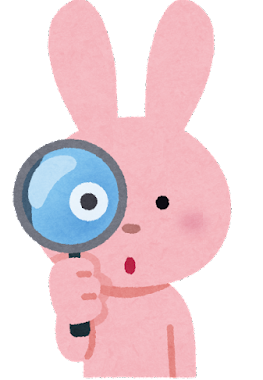
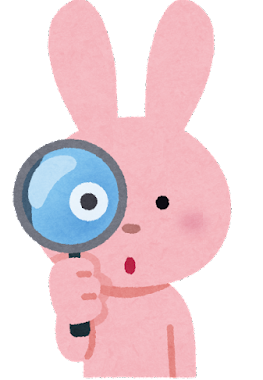
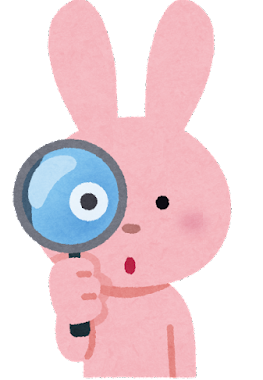
特に印象的なのは、彼があるキャット化した猫を抱き上げるシーン。
そこには、かつての仲間を想う悲しみと、猫への純粋な愛情が同居しています。
読者はその瞬間、恐怖よりも“哀しみ”を強く感じるでしょう。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』がただのギャグホラーにとどまらず、人間ドラマとしての深みを持つのはこの構成ゆえです。
一方で、相棒のカオルは現実的で冷静な女性。
彼女はクナギの猫への情を諌めつつ、理性的な判断で行動します。
この対比が『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』にバランスを与えており、読者はクナギの危うさを客観視できる立場を得ます。
また、カオル自身にも猫への複雑な感情があり、過去のトラウマをほのめかす場面も。
そうした人間側の感情のゆらぎが、終末世界にリアリティを与えているのです。
さらに、物語が進むにつれて登場する猫たちは、それぞれ個性豊かで象徴的。
- 無邪気にすり寄ってくる「野良の子猫」
- かつての人間の習慣を模倣する「元人間の猫」
- 廃墟の中でリーダーのように振る舞う「大柄な黒猫」
どの猫も単なるマスコットではなく、物語の進行やキャラクターの心情を映す存在として描かれています。
たとえば、黒猫が登場する場面では「孤独」「不吉」といった象徴性が強く、読者の心理に深い影を落とします。
クナギと猫たちの関係性は、“愛することの危うさ”そのもの。
つまり『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、「好き」という感情がもたらす狂気を描いているとも言えるのです。
人類を滅ぼすのはウイルスではなく、「かわいい」という感情の暴走なのかもしれません。
\ニャイト・オブ・ザ・リビングキャットを観るなら無料で観れるABEMAがオススメ/


作画・演出・セリフの魅力を徹底分析
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のもうひとつの大きな魅力は、ビジュアル演出の完成度の高さです。
メカルーツによる作画は、ただ可愛いだけではなく、ホラーとしての緊張感を巧みに両立させています。
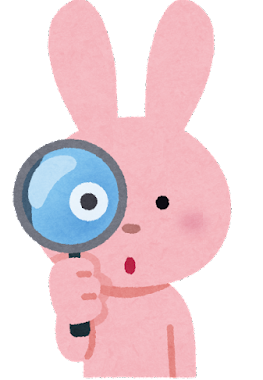
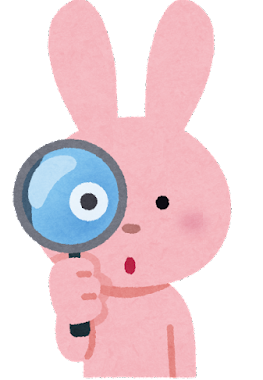
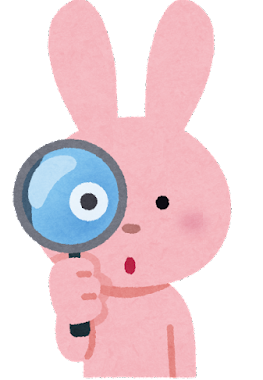
まず注目すべきは静寂の描き方!
ホラー漫画の多くは音を視覚的に表現しますが、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』ではあえて無音のコマが多用されています。
ページ全体が真っ白に近い構成の中で、わずかに描かれた猫の姿が浮かび上がる。
その「間」が読者の想像力を刺激し、恐怖を増幅させるのです。
また、猫の毛並みや瞳の描き込みも異常なほどリアル。
その繊細なタッチが、可愛さを通り越して恐怖を感じさせるほどです。
まるで神聖な存在を目にしているような感覚になり、「触れてはいけないもの」に見えてくる瞬間があるのは、作画力の高さゆえでしょう。
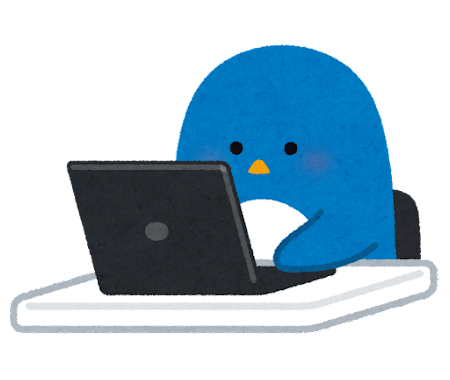
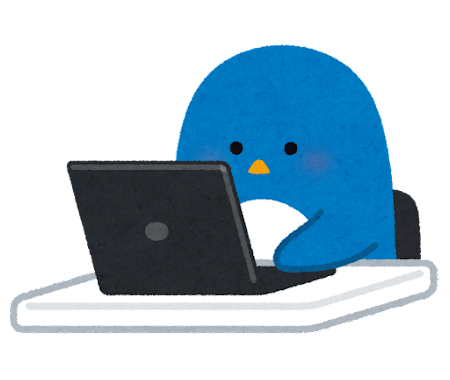
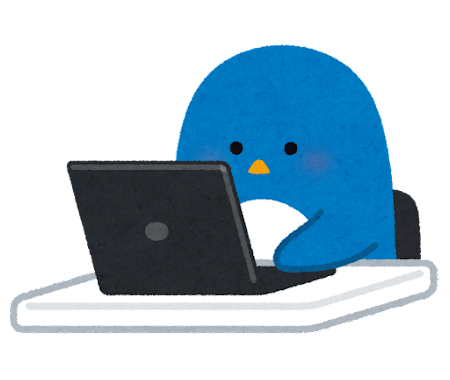
さらに、メカルーツの画面構成には映画的なカメラワークの要素も多く見られます。
遠景で群れを描き、次のコマで猫の瞳をクローズアップする。
この緩急の演出が読者の視線を自然に導き、ストーリーに没入させます。



まさに絵で語るホラー!
セリフ面では、ホークマンの脚本センスが光ります。
印象的なのは、登場人物たちのセリフが極端に少ないこと。
説明を排し、沈黙の中に感情を詰め込むことで、読者が想像する余地を残しています。
たとえば、クナギが猫を見つめながら発する「かわいいな……」という一言。
その短い台詞の裏には、“滅びの予感”と“抗えない愛情”が同居しており、読む者の心を静かに締め付けます。
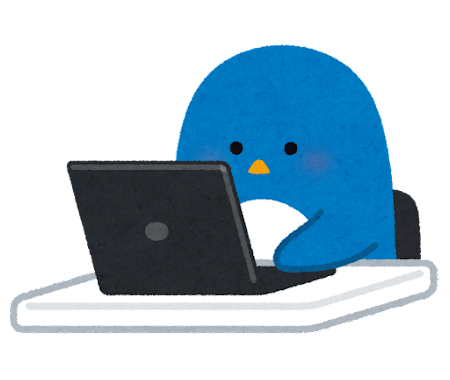
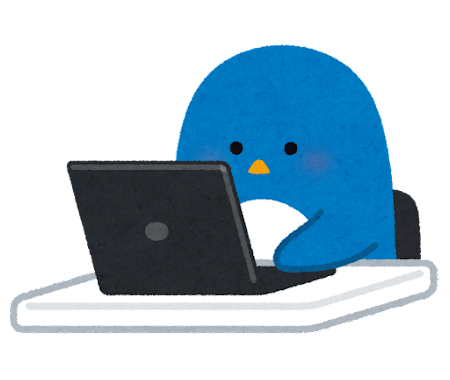
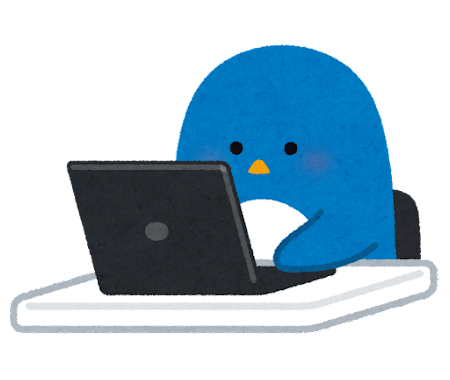
また、キャット化した人々の声が一切描かれないのも巧妙な演出。
彼らはただ「にゃー」と鳴くだけ。
しかしその鳴き声の裏に、「助けて」「もう楽になりたい」といった人間の感情が潜んでいるように感じられる。
セリフの少なさが、逆に強烈な余韻を残しているのです。


『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』が多くのファンを魅了する理由。
「かわいい」という普遍的な感情を、恐怖の文法で描いているから。
猫たちは決して悪ではありません。
むしろ、純粋で、無垢で、ただ“愛されたいだけ”の存在。
けれどその純粋さが、人間にとっては致命的な誘惑になる。
この愛の暴走とも言えるテーマこそが、怖カワイイの本質です。
そしてクナギというキャラクターは、その狭間で揺れ動く人間の弱さを象徴しています。



理性では抗えない感情、愛ゆえの破滅…
それを描き切っているからこそ、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は単なるギャグホラーを超えた哲学的ホラーとして読者に刺さるのです。
猫ゾンビが人気の理由!ファンの感想と今後の展開予想


怖カワイイという一言では語り尽くせないほど、
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は多くの読者の心を掴んでいます。
猫ゾンビという突飛な設定ながら、そこに描かれるのは“癒しと恐怖”、“愛と依存”といった複雑な感情の交錯。
この章では、この作品がなぜここまで人気を集めているのか。
その理由をファンの声やSNSの反応からひも解き、さらに今後の展開まで徹底的に予想していきます。
SNSで話題の「猫×ホラー」ブームを検証
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』がここまで注目を集めている背景には、近年の「猫×ホラー」ブームがあります。
- 癒しの象徴=猫
- 恐怖の象徴=ゾンビ
一見、真逆のジャンルである2つを融合させた『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、SNSを中心に驚きの声とともに拡散されました。



この発想天才!



怖いのに可愛いって何!?
XやInstagramでは、連載当初から「#ニャイトオブザリビングキャット」「#猫ゾンビ」といったハッシュタグがトレンド入り。
特に印象的だったのが、「ゾンビに噛まれると死ぬ」のではなく、「猫にスリスリされると猫化する」という設定。
その奇抜なアイデアは、ホラー漫画ファンだけでなく、猫好き層まで一気に巻き込む結果となりました。
また、ホラー作品でありながら、全体にどこか“シュールな笑い”や“優しい絶望感”が漂っているのも特徴。



怖いのにページをめくる手が止まらない!



癒しと狂気のバランスが絶妙!
このような意見も多くホラー漫画初心者でも読めるホラーとしても人気を集めています。
さらに、世界的にも「猫」を題材にした作品は根強い人気があり、海外でも話題に。
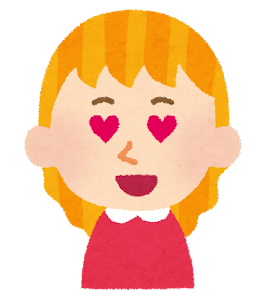
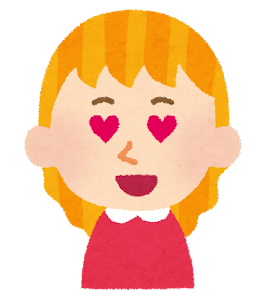
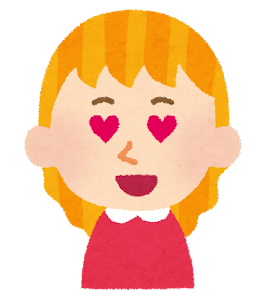
日本らしい発想力だ!
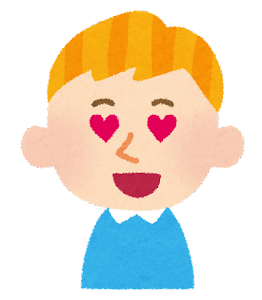
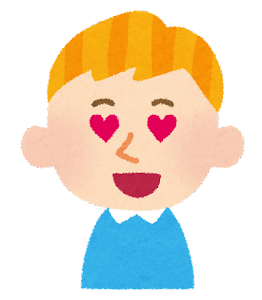
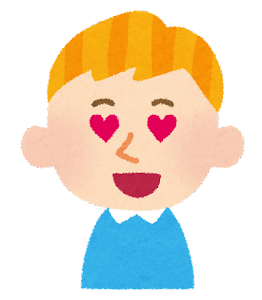
ゾンビ映画に飽きてたけど、これは新鮮!
海外のSNSではこのようなコメントも多く見られ、ネコ×終末×コメディという独自ジャンルを確立した作品として高い評価を得ています。


読者・視聴者のリアルな反応まとめ
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の読者レビューを見ていくと、作品の魅力を語る声は非常に多彩です。
特に目立つのが、「猫好きが読むと精神的にやられる(笑)」という意見。
猫がかわいすぎて破滅する世界という設定が、猫を溺愛する人ほど刺さる構成になっているのです。
・この世界なら、私も喜んで猫にスリスリされたい
・ゾンビよりも猫の可愛さの方が脅威って発想がすごい
・ホラーなのに読後感はふんわりしているのが最高
このように、ホラー作品なのに癒されるという矛盾した感情を呼び起こしています。
一方で、作品の奥には人間社会への風刺を感じ取る読者も。
「猫化=個の喪失」と捉えることで、現代社会での同調圧力や孤独、承認欲求といったテーマが見えてくるという意見もあります。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、単なる“猫ホラーギャグ”ではなく、深読みすればするほど現代的なメッセージを孕んだ哲学的作品でもあるのです。
そして、作画の美しさにも多くの称賛が寄せられています。
- 毛並みの質感がリアル
- 表情の描き分けが秀逸
- 恐怖と可愛さが同居している
絵の完成度が高く、1コマ1コマがアートとして楽しめる点も評価されています。
さらに、2020年代に入り「ゾンビ=人間の狂気を映す鏡」という解釈が浸透したことも人気の後押しに。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』では狂気の代わりに愛らしさが蔓延していくという構造になっており、「これまでのゾンビ作品の真逆を行く逆転構図が斬新」と専門家や批評家からも注目されています。


今後の展開や続編の可能性を予想
物語自体まだまだ広がる余地を残しています。
現在のストーリーは「キャット化ウイルスの拡散」を軸に展開していますが、今後は猫化した世界で生きる人間や猫と人間の共存ルールなど、より社会的・哲学的なテーマへ発展する可能性も。
原作者と作画のコンビは、これまでも個性的でメッセージ性の強い作品を手掛けてきました。
そのため、今後の展開では「単なるホラー」や「ギャグ」では終わらない、猫と人間の関係そのものを問うような深みが加わっていくと考えられる
さらに、ファンの中では「スピンオフ」や「猫視点の物語」を望む声も多数。
「猫側から見たキャット化の世界」や「クナギたちがいない地域での別視点ストーリー」など、
多角的な展開ができる余白が多いのも、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の強みです。


『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』がここまで多くのファンを惹きつけるのは、単なる猫の可愛さやホラーのスリルではありません。
そこにあるのは、愛と執着の紙一重な関係性です。
猫たちは人間を襲っているのではなく、「ただ愛情を注いでいるだけ」。
その結果、人間は理性を失い猫として生まれ変わる。
この構図は、どこか悲しくも美しい。
そしてその愛の暴走こそが、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の最大のテーマなのです。
ファンの間では「もしこの世界にいたら、抵抗せず猫にスリスリされたい」という声すら上がるほど、猫ゾンビたちの魅力は人々を虜にしています。
怖カワイイという一言では片づけられない深い余韻。
それが『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の真の魔力であり、今後の展開への期待を高める理由でもあります。



スピンオフ、グッズ展開など、これからの動きからも目が離せない!
癒しと恐怖が共存する猫世界は、まだまだ人々の心を掴み続けていくでしょう。
【ネコ好き必見】『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は怖カワ?あらすじ・見どころ・猫ゾンビの魅力を徹底紹介!まとめ


『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、ホラーと癒しを融合させた唯一無二の猫ゾンビエンタメです。
あらすじから見どころまで、すべてが斬新で、読むほどに「怖カワイイ」魅力に引き込まれます。
他のゾンビ作品とは異なり、『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は恐怖よりも愛らしさを中心に描いています。
猫にスリスリされると猫化するという奇抜な設定が、ホラーの緊張感と猫の癒しを絶妙に両立。
その結果、読む人の心をくすぐる「優しい終末感」が生まれているのです。
あらすじの中で描かれるキャット化ウイルスの拡散や、主人公たちのサバイバル劇は一見シリアス。



しかし、その中に散りばめられた猫たちの仕草や表情が圧倒的な癒しを与えます。
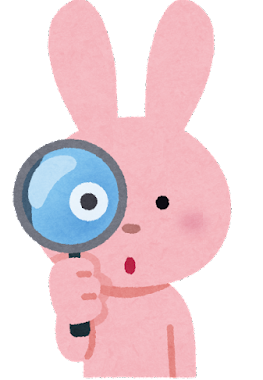
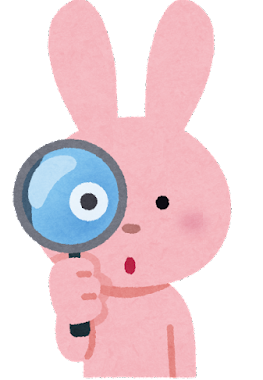
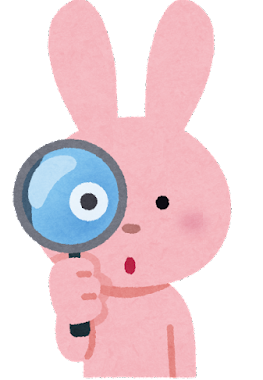
まさに、怖いのに癒されるという矛盾した感覚こそが『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』の最大の見どころ。
猫好きもホラーファンも満足できる構成になっており、読後には不思議な余韻が残ります。
つまり『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、あらすじを知るだけでもワクワクし、見どころを追うほどに奥深さを感じる傑作です。
猫の可愛さとゾンビの恐怖をここまで自然に融合させた作品は他にありません。
怖カワイイという新しいジャンルを切り開いた『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』を、ぜひ一度その目で確かめてみてください。
\ニャイト・オブ・ザ・リビングキャットを観るなら無料で観れるABEMAがオススメ/